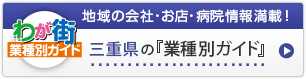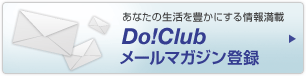熊野市特集
[三重県]
本市は、紀伊半島の南東部に位置し、津市(県庁所在地)までは約120キロメートル、名古屋市まで約190キロメートル、大阪市まで約160キロメートルの距離にあります。
市の面積は373.35平方キロメートルと県下29市町中4番目の広さで、その約88パーセントを豊かな森林が占めています。
気象環境は温暖多雨が特徴で、年間の平均気温は17度前後と温かく恵まれた気象条件にある一方で、降雨量は年間3,000ミリメートル前後と多く、集中豪雨や台風の常襲地域でもあります。
熊野市のいいトコ!!
熊野市で憩い・楽しむ
熊野大花火大会
熊野大花火大会は、初精霊供養の花火を起源とし、約1万発を打ち上げる紀州最大の花火大会です。『鬼ヶ城』や海上での自爆花火など豊かな自然を活かした大迫力の名物花火が、夜空のみならず熊野灘をも舞台として繰り広げられます。鬼ヶ城の大岸壁に響き渡る轟音と、海上花火ならではの“足”の長さなど、他に類を見ない花火として、例年全国各地から十数万人の大観衆で賑わっています。

獅子巖
海岸の隆起と海蝕現象によってうまれた奇岩で、高さ25メートル、周囲210メートルの巨岩です。昔から南側に位置する神仙洞(しんせんどう)の吽(うん)の岩(雌岩)に対して阿(あ)の岩(雄岩)といわれ、このそばを流れる井戸川の上流にある大馬神社の狛犬にたとえられています。このため、大馬神社では今も狛犬が設置されていません。

七里御浜海岸
熊野市から紀宝町に至る約22キロメートル続く日本で一番長い砂礫海岸で、これまでに「日本の渚百選」や「21世紀に残したい自然百選」などに選ばれています。また、アカウミガメの上陸地としても知られています。

熊野市の名所・文化
熊野古道
熊野古道は平成16年7月7日「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されました。
参詣道の一つである「熊野古道・伊勢路」はお伊勢参りを終えた旅人たちが「熊野三山(本宮・那智・速玉)」や「西国三十三所詣で」のために巡った巡礼の道です。
代表的なルートは紀伊半島を西回りする『紀伊路』と、東回りの『伊勢路(東熊野街道)』がありますが、前者は平安末期から鎌倉期にかけて盛んに行われた皇族らの御幸ルートで、道筋には休憩所を兼ねた王子社がまつられていました。これに対して後者は、江戸時代に伊勢参宮を終えた旅人達が辿ったルートで、いわば庶民の道でした。

花の窟
花の窟は720年(奈良時代)に記された日本最初の歴史書である『日本書紀』の神代第一で「国産みの舞台」として登場しています。この地は熊野三山信仰に先立つ古代からの聖地「イザナミノミコトの墓稜」として重要な意味を持っており、まさに日本人のルーツといえる場所です。歴史書には花の窟から御神宝を本宮大社へ移したことが書かれています。日本書紀に記されている事柄そのままに、今も毎年2月2日と10月2日には、例大祭が行われ、多くの方が参拝に訪れます。

熊野市紀和鉱山資料館
紀和町の鉱山の歴史は古く奈良時代、東大寺の大仏が造られた時も紀州地方から多くの銅が献上されたと言われています。昭和53年に閉山したこの鉱山の歴史を紹介しています。
| 電話番号 | 0597-97-1000 |
|---|

熊野市の特産・名物
みかん
熊野灘からの潮風とともに温暖な気候のもとで育つ熊野のみかんは、糖度が高く、口に入れるだけで甘さが広がります。熊野市は四季を通してさまざまな種類のみかんが栽培されています。

熊野の梅干し
熊野地域でとれた青梅を丁寧に天日干しにして、低塩に漬け込み赤しそだけで色付けた、旨味と香りは昔懐かしい味です。保存料等は一切使用していません。

さんま
熊野灘のサンマ漁の歴史は、古く江戸時代にさかのぼります。三陸沖から南下し、秋も終わりごろ熊野灘沖に姿を見せるサンマは、ほどよく脂がぬけ、くせのないさっぱりとした寿司ネタになります。
その他、カツオやサバ・イワシなど、様々な種類の魚が獲れます。