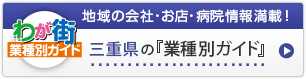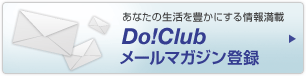明和町特集
[三重県]
町内からは、数多くの遺跡や古墳が発見され、この地の歴史が大変古いものであることを物語っています。7世紀末、天武王朝の頃には伊勢神宮に仕える斎王の住まう斎宮ができ、その規模や出土品から、中世にいたるまでのあいだ、三重県南部の産業・文化の中心地であったことがうかがえます。
奈良時代以来、明和町域は神宮領に属し、多くの御園が置かれ、また、江戸時代には藤堂藩・鳥羽藩・紀州藩・神宮領と多くの藩に分割して統治されていました。現在の町南部を通る伊勢街道はお伊勢参りの人々で賑わい、当時は宿場町として、また伊勢平野の中心穀倉地帯として栄えました。
明和町のいいトコ!!
明和町で憩い・楽しむ
斎宮のハナショウブ群落
明和町の町花で、別名「どんど花」。毎年、5月下旬~6月上旬にかけて、濃紫色の美しい花が咲き誇ります。平野に群生しているのは珍しく、国の天然記念物に指定されています。

大淀海岸ふれあいキャンプ場
白砂青松で有名な大淀海岸が眼前に広がるキャンプ場。心地よい松林の中、バンガローやテント、カーサイトで心ゆくまでアウトドアライフが満喫できます。夏期には海水浴も楽しめます。

斎王まつり
明和町の花・ノハナショウブが花咲く6月に開催される大イベント。さいくう平安の杜をメイン会場として、平安時代の王朝絵巻が繰り広げられます。
例年、多くの出店が並ぶ「斎王市」や「いつきのみやマーケット」にも、県内外から多くの人が集まります。また、「出発式」をかわ切りに、次々と厳かな儀式が再現されます。なかでも「斎王群行」は、圧巻のひと言。斎王をはじめ、女別当・内侍・近衛使など総勢約120人が路を往き、都から遠く離れた伊勢の地へと群行する平安の一幕が、色鮮やかに蘇ります。

明和町の名所・文化
斎宮歴史博物館
史跡斎宮跡地内の北西部に建てられている県立の博物館です。館内は2つの常設展示室と映像展示室があり、「文字からわかる斎宮」「ものからわかる斎宮」をテーマとした展示のほか、斎宮の制度や斎王のくらしをショートムービーで見ることができます。また、知識がなくても楽しく遊べる土器パズルなど、子どもから歴史通、斎王ファンまでが楽しめる内容が満載。ユニークな趣向の展覧会も、年に数回開催されます。
| 所在地 | 明和町大字竹川503 |
|---|---|
| 電話番号 | 0596-52-3800 |

いつきのみや歴史体験館
斎王をはじめとする王朝人生活をさまざまなプログラムで体験できる施設です。「斎宮跡歴史ロマン広場」の一角にあり、その建物は「寝殿造(しんでんづくり)」と呼ばれる平安貴族の邸宅をモデルにしています。
十二単(じゅうにひとえ)や厳かな直衣(のうし)など平安装束の試着体験や、斎王が乗った輿(こし)である葱華輦(そうかれん)の試乗体験、蹴鞠(けまり)など古代の遊び体験、年中行事にちなんだ小物づくり体験など、体験メニューが盛り沢山。
秋には寝殿造りの建物を背景に名月を愛でる雅な催し「いつきのみや観月会」が行われます。
| 所在地 | 明和町斎宮3046-25 |
|---|---|
| 電話番号 | 0596-52-3890 |

水池土器製作遺跡
斎宮で使う土器が作られたとされる奈良時代の遺跡。当時の土器の製作工程がわかる、全国でも珍しい遺跡です。広さは約1ヘクタール。国の史跡に指定され、一部が復元・整備されました。

明和町の特産・名物
あなご寿司
祝い事のある“ハレの日”に食卓を満たしたという、身の厚い穴子寿司。伝統の味を商品化した「穴子寿司玉手箱」は人気の名産品。

めい姫の十二単バウム
平成27年11月全国から明和町の特産品を使ったお土産のアイデア(レシピ)を募集し、最優秀賞作品を商品化。斎王を装い「十二単」を表現するために1層1層丁寧に焼きあげたバウムクーヘンです。

斎王べんとう 斎王の宝箱
王朝時代の食生活を復元。伊勢湾で捕れた季節の魚や鳥、野菜など新鮮な素材を30種類近く盛り込んだ上品でおいしい弁当です。